top of page
検索


それでもプロか? その2
ある信徒さんが西光院を訪ねてこられた。 予定よりも時間が懸かったとおっしゃる。 JR高田駅から乗ったタクシーの運転手が竹内の西光院を知らなかったらしい。 住所や電話番号を伝えても上の空、ナビもついているのに使わない。 それってプロ意識? 実は使い方を知らないだけ? かなり遠回りをした挙げ句、近所でウロウロしていた様子。 途中で料金メーターは停めたそうだが、気分が悪いものだ。 「それでもプロか?」 というクレームの電話を入れようか迷ったが、 実はこの種の話は、枚挙に遑がない。 以前も、中陰参りに京都から7回通われた女性が涼しい季節にも関わらず、 毎回大汗をかいてこられるので「駅から歩いておられるのですか?」と尋ねると 駅からタクシーだという。 迷った挙句、ヘンなところで降ろされましたとのこと。 読者に断っておくが、西光院は秘境ではない。 タクシーの需要が少ないこの地域で走っている車があるだけで上等だと思うし、今どきベテランなどいないことは知っている。 ナビがあるなら使えばいいのに。 今どきスマホもあるのに。 この時、ドライバーは「知らない場所に行く

中村法秀
1月14日読了時間: 4分


それでもプロか?
ある信徒さんがお母さんの満中陰に合わせて両親の位牌を新調された。 インターネットを通じて発注されたところが、写真のような位牌ができあがってきた。 夫婦で文字の位置がズレているのを不思議に思って刹那、あきれた。 ご主人の方にだけ「位」が入っている。 仏弟子として生前に受ける名前が戒名だが、 位牌にする場合は、極楽へ往生された結果として得られる「位号」(名前)であることを表している文字だ。 夫婦位牌なら、それぞれの戒名の下に半角程度の空白を置いて刻むか、二人の戒名の下に1つだけ入れる。 写真のように片方にだけ入れることはない。 しかもこれは戒名の一部という扱いで入れている。 喪主さんにそのことを伝えると、 「前もって住職さんに確認せずにすみません」と謝られる。 そこじゃない。 私「ダメなのは仏具屋です。これどこの仏具屋ですか? あぁ…ネットで?」 喪主さん「原稿を確認されたのでそこで校正を入れなかったこちらが悪いと思います」 それは正論だが、仮に原稿で依頼者が分からずにそう書き込んできても、 作る側がプロとして、「位」は書式的に最下段で入れるものとい

中村法秀
1月8日読了時間: 2分

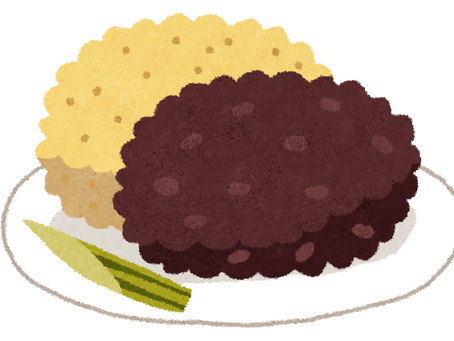
お先に...
近所の和菓子屋さんでの出来事。 行列が出来るほどの名物。 久しぶりに並んだ。 コロナ以来、入店は1組ずつの制限。 こじんまりとした店内でもあり、結果的には注文・手渡し・精算がスムーズなのだろう。 店先で数組の客が待つことになる。 そのために長イスが用意されている。 わずかな時間ながら前後の見知らぬ客同士が会話することも。 年配の男性と、片や家族連れのご婦人が話している隣に腰かけた。 家族連れは横浜からお越し。お寺へ観光しての帰り。 男性が住まいを聞かれて、大阪府の北の方、京都に近い所からと答えて驚かれている。 車で1時間。お餅を買うためだけに?と。 家族みんなが好きでして、と応じている。 男性は、おいしいですからね、どうぞ今度は横浜から新幹線で(わざわざ)買いにいらしてください、と笑いが起こる。 2組ともお店に入られて、独り店先に居て秋風に揺られる。 良いなぁと微笑んだ。 たまたま居合わせた人と軽く談笑することの妙。 最近はそういう場面や経験をしなくなって久しい。 先に出てきたその男性が、立ち上がる私に 「お先に...どうも」 と

中村法秀
2025年10月27日読了時間: 2分


仏壇の中に遺影を祀るとダメ?
「知り合いから『遺影を仏壇の中に置いてはダメよ』と言われて、急に気になりまして」 との言。 日常的に受ける質問ですが、今年の盆は、複数の方から質問されました。 私の答えは、 「全く問題ありません。気にしなくていいです」 です。 それらの指摘は、根拠となる教えのバックボーンもなく述べられています。 信仰上の態度を理由にしていても、大したことは見当たりません。 全く揺らぐ必要はなく、無視して良い意見です。 試しにネットの動画サイトで「仏壇」「遺影」で検索してみると、出るわ出るわ。 各宗の坊さん、仏壇屋・葬式屋、マナー講師、霊能者といった方々が入り乱れ、種々雑多な意見を述べていますけど、結局どれもこれも論拠がないんです。 (多くが自身の中で矛盾し、破綻しています) 仏壇は仏さまの世界を表しているから、どうのこうの。 世俗の衣服姿が写っているから、どうのこうの。 生存者が一緒に写っていたら、どうのこうの。 (それがどうしたんでしょう?) 仏壇の上は聖域なので、どうのこうの。 日当たりが良い場所は、どうのこうの。 処分する時は、どうのこうの。...

中村法秀
2025年8月27日読了時間: 4分


アジサイの季節
今週に入って一気に色づいてきました。 見るたびに色が変化して印象が変わるのが楽しいです。 花言葉の一つに「移り気」があるのはそのことを言うのでしょう。 土中の養分を吸い上げながら色艶を変化させてやまない、その瑞々しいすがたを私は愛おしく思います。...

中村法秀
2025年6月10日読了時間: 1分


第7章「立教開宗」
【解説】 善導大師の御文を改めて拝読すること三度。 『彼の仏の願に順ずるが故に・・・』と呟かれたかどうかは分かりませんが、「そうか、それで良いのだなぁ」と腑に落とされた瞬間があったに違いありません。 一切経を五度も読まれ、これはと思うものはさらに三度目を通されて、何度も拝読...

中村法秀
2022年7月8日読了時間: 1分


『仁誉編 月参り頒布版 法然上人行状絵図』(2022年・西光院)
祖師の最もスタンダードな伝記である『法然上人行状絵図』(四十八巻伝・勅修御伝)。 西光院では、平成27年(2015)11月より令和3年(2021)3月までの歳月をかけて48章に抜粋して切り出し、月参り・年忌参りなどで拝読してきた。 底本を浄土宗聖典版に依り、早田哲雄...

中村法秀
2022年6月13日読了時間: 1分


『元祖大師御法語 前篇・後篇(西光院版)』 (2022年)
大正4年(1915)に総本山知恩院が発行した法然上人の御法語集で、教えの要点を抽出したもの。法話の題材に選ぶなど、教師・檀信徒に最も親しまれており、重要な役割を果たしている。 西光院では、平成22年(2010)から6年間、前・後篇の都合62章に対し、住職が独自に語句調べ・現...

中村法秀
2022年6月13日読了時間: 1分


第6章「釈迦堂参籠と南都遊学」
【解説】 法然上人24歳の時、一度比叡山を降りられ、先ずもって嵯峨の釈迦堂を訪ねられます。 「生身(しょうしん)の釈迦」として尊崇を集めているそのお釈迦さまに対面し、教えを請う思いでいらしたことでしょう。 また同寺は、当時では珍しく民衆に至るまで境内に参詣を許された珍しいお...

中村法秀
2022年5月26日読了時間: 1分


第5章「黒谷修学」
【解説】 法然上人は、戒律の専門家である叡空上人を師匠に求めて黒谷に隠遁されました。師匠の許で修行に専念し、一切経を読み込む中で盛んに議論もなされたようです。 ある時、「戒律の魂は何に宿るのか」という議論になり、師は「心」であると言い、弟子は「体」だとしました。...

中村法秀
2022年3月22日読了時間: 1分


第4章「登嶺、隠遁の志」
【解説】 叔父がその才能を見込んだように、比叡山に登ってからも勢至丸は天才ぶりで周囲を驚嘆させます。 最初の師・源光さまのもとで、手ほどきを受ける前に古来の問題とされる点を指摘して見せたのです。物事の本質を素早く見抜く力でしょうか。...

中村法秀
2022年3月9日読了時間: 1分


第3章「母との別れ」
【解説】 「父遺言のことありければ」とは言え、無論、定明の追撃から避難したといえるでしょう。勢至丸は15歳になり、元服か出家かの決断を迫られたのだと思います。 しかしそれら世俗の通り一遍の邪推をよそに、母上を説得される言葉の中に勢至丸の強い意志が感じ取れます。母一人を置いて...

中村法秀
2022年3月3日読了時間: 1分


第2章「父の死」
【解説】 一口に、武士同士の争いで…と片付けるとあまりに不可解な事件。 「荘園」という、バックに莫大な権益を持つ存在があり、在地の管理を任されたエリート武士である明石定明(預所)と、地元の名士である父上・漆時国(押領使)とのプライドを懸けた軋轢があったと思われます。...

中村法秀
2022年2月18日読了時間: 1分


第1章「ご誕生」
法然上人のご生涯を記した伝記のうち、もっともスタンダードなものが『法然上人行状絵図』(48巻)です。 上人没後100年頃(14世紀初期・鎌倉時代)に編纂されました。原本は、浄土宗の総本山知恩院にあります(国宝)。 原典は四十八巻もある大部です。それを抜粋して月参りで拝読を進...

中村法秀
2022年2月10日読了時間: 2分


仰ぐ視線
こんにち、お寺でもイス席が普通になった。 生活様式が変化したのであって、抗えない。 老いも若きもイスの生活なのだから、 参詣を受け容れる側としてもイスを用意せずにはいられない。 いかにも「仕方なし」という書き方だが、 私も日ごろ、自分だけのお勤めでイスに座ってしまっている。...

中村法秀
2022年1月18日読了時間: 1分


『法然上人伝記(醍醐本) 中村法秀ノート』 (2021年・私家版)
法然上人をきちんと紹介している本が少ないことを以前にも書いた。 今回は史料そのものの紹介である。専門的な内容、しかも私家版。 恐縮至極ではあるが、もしこのページを見て、浄土宗僧侶はもちろん、一般の方でもその気になって読んで頂けるならば、幸いと思って紹介する。...

中村法秀
2022年1月11日読了時間: 2分


令和4年
新しい年が明けました。おめでとうございます。 新春早々、コロナの新種(オミクロン株)のために、やむなく檀家総集会を中止する決定を総代さまと合議し、その書類作成に追われています。 昨年中も行事は、春秋彼岸会、施餓鬼会、観音・薬師尊の縁日、地蔵尊の縁日、十夜・仏名会を実施できま...

中村法秀
2022年1月4日読了時間: 1分


三千佛
令和3年(2021)12月5日(日) 14時より法要、15時より涅槃図の絵解きをいたします。 「仏名会」(ぶつみょうえ)と呼ぶこともありますが、当山では三千佛と呼び慣わしています。年末にあたり、礼拝懺悔(らいはいさんげ)する法要です。...

中村法秀
2021年11月4日読了時間: 1分


秋季 彼岸会
9月25日(土) 14:30~おつとめ 今回もコロナウィルス予防の観点から、 檀信徒のみの参詣とし、一般の参詣はお断りします。

中村法秀
2021年8月26日読了時間: 1分


施餓鬼会(せがきえ)
来たる8月6日(金)午後2時より、お盆の施餓鬼会を行います。 日ごろ回向の薄い霊位や、月参りから遠ざかっておられる施主様などは、 この機会にご参詣・結縁くださいますようご案内いたします。 なお、お塔婆は、3,000円・5,000円・10,000円の三種類です。...

中村法秀
2021年7月16日読了時間: 1分
bottom of page